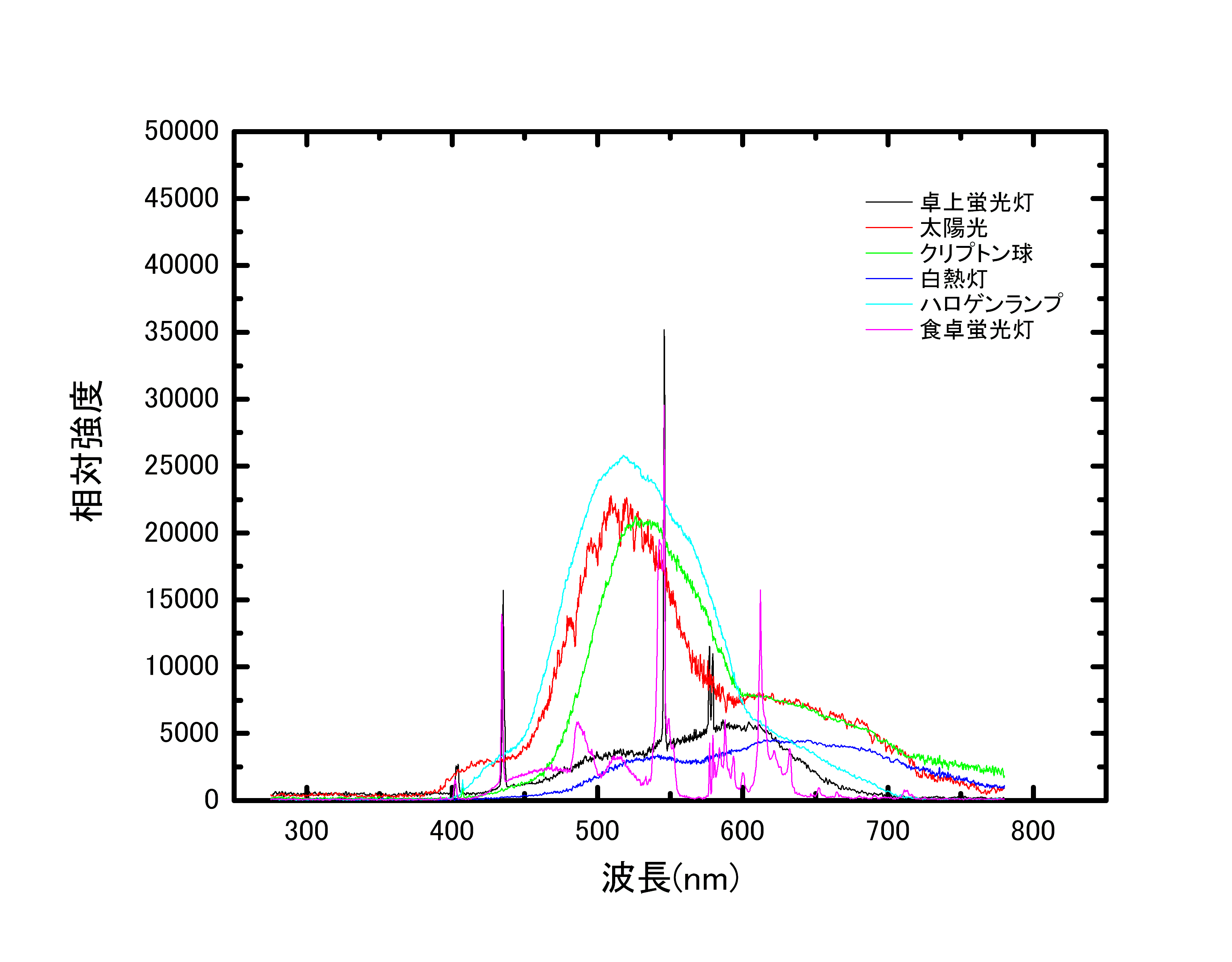
| 【科学のつまみ食い】 | 色々な蛍光灯 | フィルター | |
| 分光器の作り方 | 太陽の光 | ||
| 分光器の校正 | 色々な光源 | ||
| 分光器を作って分光しよう | |||
【吸収スペクトルの測定】
さて、 今までは発光スペクトルとして、太陽光や蛍光灯、その他の電球などのスペクトルを測定してみました。下に再度、それらのスペクトルを掲載します。このように分光器を使用すると色々な光を測定することができます。ところで、皆さんはセロファン紙をご存知ですよね。赤とか、青とか、黄色とか、色々な色のセロファン紙があります。このセロファン紙は、例えば、赤いセロファン紙ならば、赤い色以外の光を吸収するので、赤く見えます。要するに赤い光のみを通過するフィルターです。ここでは、このセロファン紙のように吸収スペクトルの測定をしてみます。
では、吸収スペクトルを測定するためには何が必要でしょうか?分光器が必要なのは言うまでもありません。しかし吸収スペクトルは自分自身が発光するのではないので、分光器以外に光が必要です。では、照明としてはどういうものが必要でしょうか。
①連続スペクトルを発光するもの
②条件によってスペクトルが変化しないもの
③なるべく広い波長範囲で発光すること
の3条件が最低必要です。これらの条件に当てはまりそうなものは、下のスペクトルから見ると、輝線スペクトルを発光する蛍光灯は却下です。では、連続スペクトルである太陽光はどうでしょうか?太陽光は天気によって明るさやスペクトルが変化するので安定していないので、これも却下です。残りの光源はいずれも上の条件を満たしますが、ここでは、太陽光に発光スペクトルの形が近いハロゲンランプを使用することにします。クリプトン球は赤い波長(長い波長)のほうは広いですが、青い波長(短い波長)のほうが狭いので却下としました。
、
ハロゲン光源を用いて、吸光分光を行った結果が下のグラフです。ハロゲン光源のスペクトルと、天体撮影などで使用される光害フィルターの吸収スペクトルを掲載しています。波長校正のために、蛍光灯のスペクトルも掲載しました。LPS-P1は丁度、蛍光灯の輝線スペクトルを遮断できるようになっています。このようにして、町の明かりを遮断して、天体の光のみを多く通すことにより、天体撮影ができます。NBN-PVのほうは、LPS-P1に比べ、多くの波長の光を遮断していることがわかります..しかし、蛍光灯の基線以外の光を多く遮断しているので、星の色が違って見えます.そういう意味ではLPS-P1の方が優れているといえます.
上のスペクトルは実際のスペクトルの吸収の割合をあらわしているものではなく、感度の校正が必要になります.そこで、上で掲載したLPS-P1とNBN-PVスペクトルをハロゲン光源のスペクトルで割ったものが吸光度(吸収の割合)になるので、この吸光度を計算してスペクトルにしてみました。それが、下のスペクトルで、フィルターの吸収の割合を表すことになります。